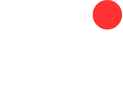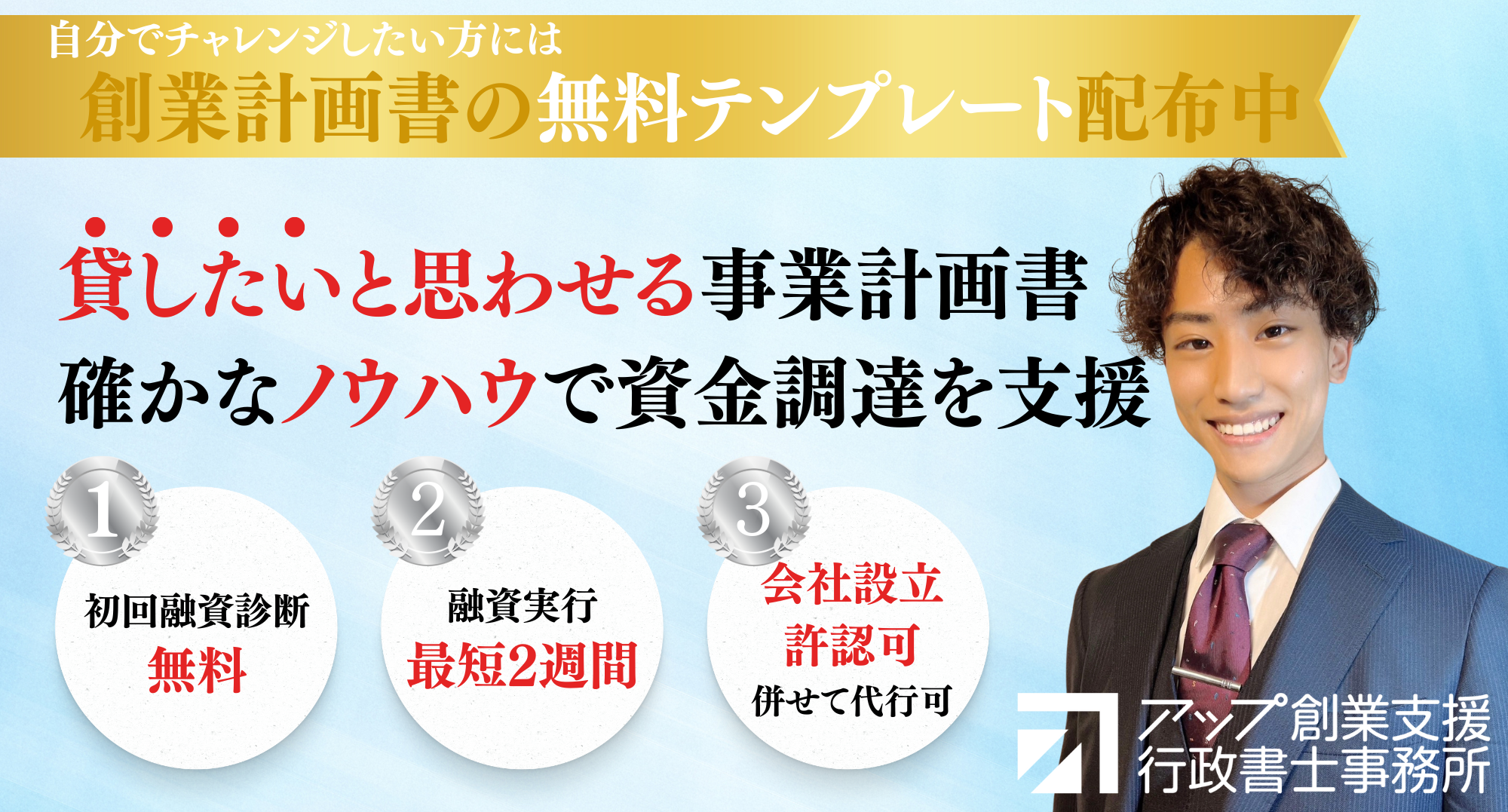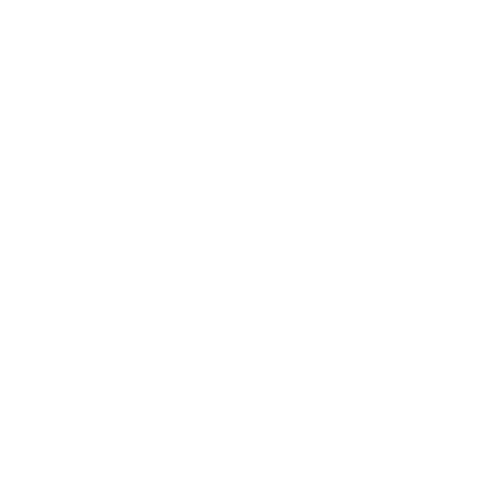行政書士が民泊の始め方を徹底解説!
最終更新日:2025/4/18
こんにちは!行政書士の梅田です。
今回は、「民泊の始め方」について主に届出やチェック要件について解説をします。
開業資金の調達方法や融資に成功しやすい事業計画書の作成方法は以下のコラムで解説してるのでこちらも併せて確認してみてください!
>民泊の開業資金の調達方法!成功しやすい創業計画書の記入例
■許認可に関するご相談■
■創業融資サポートも■
自己資金、個人信用情報、借りられる金額、事業計画書、面談…
その悩み全部お任せください!
【無料】の融資診断から利用できるサポートはこちらからチェック
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
民泊(住宅宿泊事業)とは
旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。
民泊には、
1.旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
2.国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
3.住宅宿泊事業法の届出を行う
の3つの形態があり、住宅宿泊事業とは民泊の一形態ということになります。
近年は、その届出の簡易さや地域の制限が少ないことで人気となっております。
民泊(住宅宿泊事業)の対象となる住宅の要件
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、設備要件と居住要件を満たしていることが必要です。
設備要件
必要な設備
届出を行う住宅には、「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」の4つの設備が設けられている必要があります。
設置場所
必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることが可能です。
公衆浴場等による代替の可否
これらの設備は、届出住宅に設けられている必要があり、届出の対象に含まれていない近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできません。
設備の機能
これらの設備は、必ずしも独立しているものである必要はなく、一つの設備に複数の機能があるユニットバス等も認められます。
また、これらの設備は、一般的に求められる機能を有していれば足ります。例えば、浴室については、浴槽が無くてもシャワーがあれば足り、便所については和式・洋式は問いません。
居住要件
対象となる家屋
届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。
(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」の考え方
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは、現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋です。「生活が継続して営まれている」とは、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません。
「入居者の募集が行われている家屋」の考え方
「入居者の募集が行われている家屋」とは、住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。なお、社員寮として入居希望社員の募集が行われている家屋等、入居対象者を限定した募集がされている家屋もこれに該当します。
ただし、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者募集の意図がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」とは認められません。
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」の考え方
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」とは、生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。
当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用している家屋であり、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これには該当しません。
「随時居住の用に供されている家屋」の具体例は以下のようなものです。
・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・休日のみ生活しているセカンドハウス
・転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家
・相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家
・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家
その他留意事項
一般的に、社宅、寮、保養所と称される家屋についても、その使用実態に応じて「住宅」の定義に該当するかを判断します。
「住宅」とは、1棟の建物である必要はなく、建物の一部分のみを住宅宿泊事業の用に供する場合には、当該部分が法第2条第1項に規定する「住宅」の要件を満たしている限りにおいて、当該部分を「住宅」として届け出ることができます。
本法において、住宅宿泊事業に係る住宅については、人の居住の用に供されていると認められるものとしており、住宅宿泊事業として人を宿泊させている期間以外の期間において他の事業の用に供されているものは、こうした法律の趣旨と整合しないため、国・厚規則第2条柱書において本法における住宅の対象から除外しています。
民泊(住宅宿泊)事業者の届出に必要な情報、手続きについて
住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る必要があります。
なお、住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行うこととしています。
届出前に確認しておくべき事項
住宅宿泊事業の届出をしようとする者は、届出の前に下記の事項等について確認をしておく必要があります。
・届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか
・マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか。規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要となります。
・消防法令適合通知書を入手しておくこと
届出事項
[1]商号、名称又は氏名、住所
[2]【法人】役員の氏名
[3]【未成年】法定代理人の氏名、住所
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)
[4]住宅の所在地
[5]営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地
[6]委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容
[7]【個人】生年月日、性別
[8]【法人】役員の生年月日、性別
[9]未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別
(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)
[10]【法人】法人番号
[11]住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号
[12]連絡先
[13]住宅の不動産番号
[14]住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
[15]一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
[16]住宅の規模
[17]住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨
[18]賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
[19]転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
[20]区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと
管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨
添付書面
法人の場合
[1]定款又は寄付行為
[2]登記事項証明書
[3]役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
[4]住宅の登記事項証明書
[5]住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
[6]「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
[7]住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
[8]賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
[9]転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
[10]区分所有の建物の場合、規約の写し
[11]規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
[12]委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
[13]欠格事由に該当しないことを誓約する書面
個人の場合
[1]破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
[2]未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
[3]欠格事由に該当しないことを誓約する書面
[4]住宅の登記事項証明書
[5]住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
[6]「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
[7]住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
[8]賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
[9]転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
[10]区分所有の建物の場合、規約の写し
[11]規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
[12]委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
住宅宿泊管理業務の委託
住宅宿泊管理業務の委託が必要な場合とは
住宅宿泊事業者は、次のいずれかに該当する場合は、住宅宿泊管理業務(法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務)を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、自ら住宅宿泊管理業務を行う場合については委託不要です。
1.届出住宅の居室の数が、5を超える場合
2.届出住宅に人を宿泊させる間、不在(※1)となる場合(※2)
(※1)日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く
(※2)住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として以下のいずれをも満たす場合は除く
[1] 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物もしくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき
(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く)
[2] 届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が5以下であるとき
なお、住宅宿泊管理業務の委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託する必要があります。また、委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、予め届出書および添付書類の内容を通知する必要があります。
住宅宿泊管理業務の委託が必要な場合の考え方
(1)住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全について
住宅宿泊事業は、人が居住し日常生活を営む空間に人を宿泊させるものであり、その適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全として、人が居住し日常生活を営むために必要な機能を維持する必要があります。具体的には、届出住宅に設ける必要がある台所、浴室、便所、洗面設備が正常に機能するものであるほか、人が日常生活を営む上で最低限必要な水道や電気などのライフライン、ドアやサッシ等の届出住宅の設備が正常に機能するよう保全することが必要です。また、空室時における施錠の確保や、住宅又は居室の鍵の管理も届出住宅の維持保全に含まれます。
(2)委託について
法第11条第1項に基づき、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合は、一の住宅宿泊管理業者に委託しなくてはならず、複数の者に分割して委託することや、住宅宿泊管理業務の一部を住宅宿泊事業者が自ら行うことは認められません。ただし、住宅宿泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者が、他の者に住宅宿泊管理業務を一部に限り再委託することは可能です。
委託義務の対象となる住宅宿泊管理業務の範囲は、法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務となりますが、届出住宅の維持保全に係る業務については、(1)を踏まえた上で、管理受託契約においてその対象範囲を明確に定める必要があります。
委託は、管理受託契約で定める住宅宿泊管理業務の実施期間の始期においてなされたものとみなされます。そのため、委託の実施により管理受託契約の締結時の書面の内容が変更となる場合には、当該始期までの間に、住宅宿泊事業者は、都道府県知事等に対して、当該変更内容を届け出る必要があります。
住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の共同住宅内にある場合や同一の敷地内にある場合等であっても、敷地が広範であるためそれぞれの住戸の距離が著しく離れている場合その他の自己の生活の本拠にいながら届出住宅で発生する騒音等を認識できないことが明らかである場合には、住宅宿泊管理業務の適切な実施に支障が生ずるおそれがないとは認められないため、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。
(3)住宅宿泊管理業者への通知について
法第11条第1項に基づき委託する場合においては、住宅宿泊事業者は委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、予め、届出書及び添付書類の内容を通知する必要があります。この際に通知する内容は、当該委託による届出事項の変更を反映する必要はなく、当該委託以前の内容を通知することで足ります。通知の方法は、電磁的な手段によることもできます。
(4)一時的な不在に関する考え方について
日常生活を営む上で通常行われる行為である生活必需品の購入等については一時的な不在に該当しますが、業務等により継続的に長時間不在とするものは一時的な不在には該当しません。
一時的な不在として認められる時間は、届出住宅が所在する地域の事情等を勘案する必要があるため、一概に定めることは適当ではありませんが、原則1時間となります。ただし、生活必需品を購入するための最寄り店舗の位置や交通手段の状況等により当該行為が長時間にわたることが想定される場合には、2時間程度までの範囲となります。
なお、住宅宿泊事業者は届出住宅を一時的に不在にする場合においても、宿泊者の安全の確保に努めることが必要です。
• 「不在」とは、住宅宿泊事業者が届出住宅を不在にすることをいいます。住宅宿泊事業者ではない他者が届出住宅に居たとしても、住宅宿泊事業者自身が不在としている場合は「不在」として取り扱われます。ただし、宿泊者が全員外出しており、届出住宅にいない場合は、住宅宿泊事業者がその間不在となっても「不在」の扱いとはなりません。
(5)その他の留意事項について
法第11条に基づく住宅宿泊管理業者への委託をしている間、住宅宿泊事業者は必ず不在にしなくてはならないということではありません。住宅宿泊事業者が届出住宅にいる間においても、「届出住宅に人を宿泊させる間、不在となるとき」の考え方は適用されます。
本条に基づかない委託によって常時届出住宅内にいる住宅宿泊事業者(※)が、清掃等の一部の事実行為を住宅宿泊管理業者ではない専門業者に行わせることは可能です。この場合は、法第5条から第10条までの規定は住宅宿泊事業者に適用されますので、事業者の義務は委託者である住宅宿泊事業者に課せられているため、住宅宿泊管理業務における違反等があった場合には、委託者の責任となります。
(※)住宅宿泊管理業者に委託をせずに住宅宿泊管理業務を自ら行う住宅宿泊事業者であって、届出住宅の居室の数の合計が5以下の者に限ります。
当事務所は、民泊の許認可申請や資金調達など幅広く開業のご支援をしております。
>民泊の開業資金の調達方法!成功しやすい創業計画書の記入例
気になった方はぜひお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
■許認可に関するご相談■
■創業融資サポートも■
自己資金、個人信用情報、借りられる金額、事業計画書、面談…
その悩み全部お任せください!
【無料】の融資診断から利用できるサポートはこちらからチェック
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
気になった方はぜひお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ

行政書士/銀行融資診断士・梅田遼翔(ウメダハルカ)アップ創業支援行政書士事務所代表。
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
【創業融資を受けたい方へ一言】
創業期のあらゆる不安に寄り添います!まずはお気軽に無料相談をどうぞ!
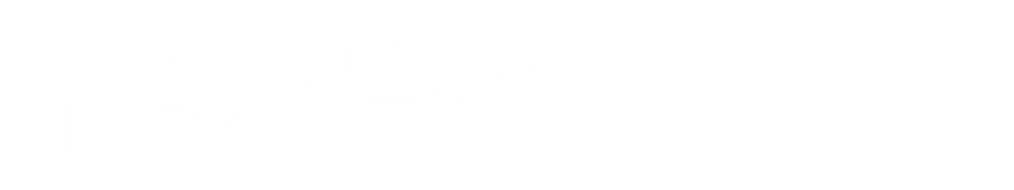
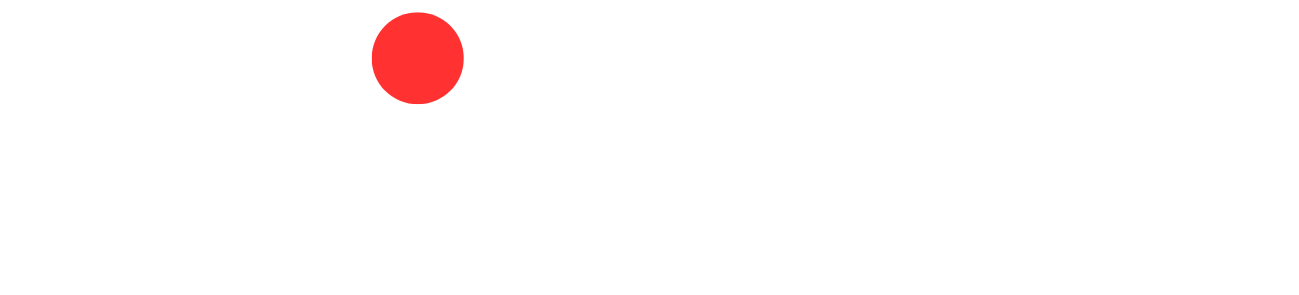
.png)